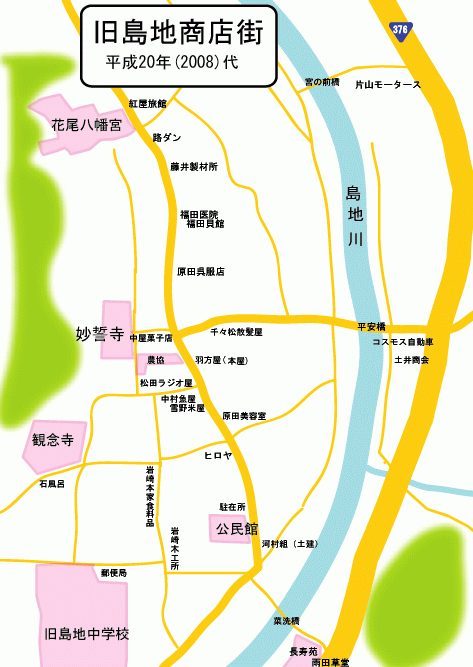
;
島地市を歩いてみるには、島地公民館をベースに歩くのが便利です。
島地市はかっては徳地を代表する商業地であった。
島地の名前の由来は不明だが、「八幡宮本紀」には
康和年(1099〜1103)には嶋地の地名が見えるとある。
平安時代、既にこの名前で呼ばれた集落があったことになる。
そのころのことは資料も乏しく村の様子を知るべくも無いが、
幕末に著わされた「防長風土注進案」によれば
「嶋地市には商家や職人家が軒を連ね、町裏にも家が多数ある。」
「市日には近郷の農商人が群集して穀類、農機具、諸産物、紙楮などを交易する」とある。
この度、機会があり、昭和10年代、昭和30年代のまだ記憶に残る町並みを
地域の方々の協力を得て記録することができた。
多少の記憶違いもあるかも知れないがその時代を示す貴重な情報となると思われる。
現在:平成20年(2008)
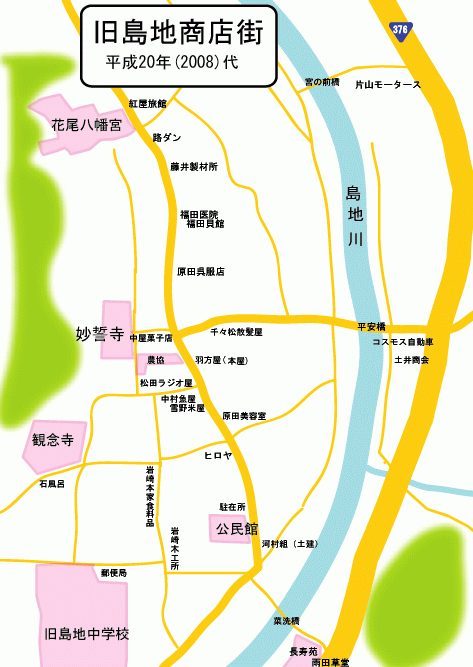 |
 |
昭和10年代(1930年代)
昭和10年代(1930年代)の島地の市の様子は、
現在80歳代の方が更にその親の世代から聞いたり、
残っていたりしたものによる語りとなります。
当時の徳地の経済力は
島地黙雷上人の為に庵を建てたり、
明星の創始者与謝野鉄幹に発行費用を提供したりしており、
地方の農村は豊かであったと思われます。
島地の市には 和紙を商う店
楮・三椏の蒸し釜、倉庫、
醤油蔵、酒蔵(造り酒屋、醤油屋)があり、
医者が3軒、
呉服屋、鋤・鍬屋も複数軒
下駄屋、代書屋、うどん屋、
面白いのは常設の芝居小屋、三味線屋、飲み屋、ビリヤードなどの娯楽もここで楽しめたようです。
出雲大社周防分院も明治の終わりに招聘しており、意気盛んだった様子がうかがえます。
また、昭和10年の島地商店街には「すずらん灯」が4基あったと聞いています。
「すずらん灯」神戸元町に昭和初年について、以降全国に広まったそうです。
島地の「すずらん灯」はどんな形だったのか?

HPで読むと全国の「すずらん灯」は戦争中の金属回収でなくなってしまったようです。