「東大寺造立供養記」(*養和建仁の記録)
(養和[1181-2]建仁[1201-4]で大仏殿完成供養が行われたのが1195であるので同時代の記録といえる。)
(原文を読み下す)
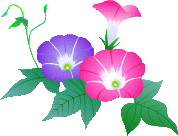
「東大寺造立供養記」(*養和建仁の記録)(養和[1181-2]建仁[1201-4]で大仏殿完成供養が行われたのが1195であるので同時代の記録といえる。) (原文を読み下す) | 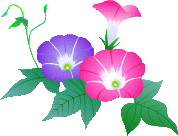 |
|
造立供養記に 而して源平合戦の時、周防国、地を払って損亡す。 故に夫は妻を売り 妻は子を売り、或いは逃亡し、 或いは死亡し、その数を知らず。 僅かに残る所の百姓も、若(も)しくは存し、若しくは亡 び、上人着岸せんとする時、国中の飢人雲集す。 上人非心を発し、船中の米を以って悉(ことごと)く施行せし む。 此の如き施行度々に及ぶの間、重ねて農料の 種を賜い、人民を生活せしむ。 爰(ここ)に、材木を巡検するの間、深谷高厳、歴覧せざるなし。 杣人等に命じて言う。 好木を求め得る輩に於いては、柱一本別に 米一石を賜うべし云々。 茲(ここ)に因(よ)りて、杣人等励心を発し、 谷峰を論ぜず、疲(つかれ)を忘れ負を贔(ひ)し(力を出し)、以って好木を求め尋ぬ。 柱一本の長さ、或いは九丈十丈、或いは七丈八丈、口径五尺四五寸なり。 一本別の作法は轆轤(ろくろ)二張を建て、以って人夫七十人を附けて、轆轤を押し、大綱を引く。 綱の口六寸、長さ五十丈なり。 五十人して綱一丈を持ち挙ぐ。 この綱二筋を柱の本と末に附けて、これを引く。 もし轆轤なければ即ち千余人、以ってこれを引かしむ。 然る間に或は数十丈の渓(たに)を埋めて、嶮難を平らかにし、或いは高大の磐石を摧(くだ)き山路を開き、或いは衆木を伐(きり)て荊棘(けいきょう:いばら)を除き、或いは大橋を構え、以って谷を通し、厳寒、水を凌ぎ、以って人力を儘(つく)す。 炎天、汗を拭い、以ってこの役に励めり。 大材あり雖(いえど)も好木は得難く、数百本を切ると雖も、纔 (わずか)に十二十本を得(う)。 所以(ゆえん)は、或いは大木の中空損し、或いは節枝多く難有り。 杣中より大河に出す、名を佐波川という。 木津より海に至る七里(三十六町を一里となす)は、水浅き故に柱 流下せず。 仍(よって)河を関て水を湛(たた)う。 七里の間に水を関く所百十八処なり。 新に河を堀、江海に通ず。 四月上旬より、七月下旬に至る水を関くの間、手足爛壊(らんかい:ただれくずれ)し、身力悉(ことごと)く、費盡(ひじん:つかいつくす)し、畢(おわ) んぬ。 凡そこれらの如き大事は、唯、一処二処に非らず、既に数百処なり。 或は東西の峯、或は南北の洞、四角八方在々処々、杣中に道を造る三百町なり。 筏組の様は普通の儀に非ず。 上人の巧みに依りて筏を操る構えなり。 葛藤(ふじかずら)を以って綱となすの間、国中の葛藤、払底し畢(おわ) んぬ。 仍(よっ)て、他国に往きてこれを採る。 筏到来 の時種々の構を儲(もう)く。 木津の河水浅けれ ば則ち「」(ママ)船四艘を以って柱の本と末に附く。 即ち柱を浮かべる秘術なり。 泉(和泉)の木津に至る時、大力車を以ってこれを載(の)せ、牛百二十頭を懸く諸官諸院有縁の人々柱を引く。 而して寺に着くや、法皇並びに女御共参詣し、法皇自ら、その綱に附かしめ、諸卿皆悉(ことごとく)綱に付きて之を引くなり。 綱の端、女御の御車に入り、女御、綱を執りて結縁せしむ。 と記している。 |